クトゥの歯車─次王─
|
さてここで云う歯車の、噛み合う場所が交差する際に 発する音とは如何なるものか。 おそらくは音なき音――しかしてそれでは語るに不自由。 そこで仮に“ことり” としよう。 それではクシュルファ・クトゥの歯車の 最初にことりとその音を奏でたのは まだその姿さえ成さぬ頃 現(いま)のクトゥの命(めい)たる篝火燃え尽きるを目前に この夏に至る日の、一等最初に産声をあげた女子(おんなご)を 次のクトゥと定めると 詔(みことのり)の発せられたその瞬間であっただろう。 死線を彷徨うほどの苦しみの果て産み落とした 我が子を左様と、空の揺篭を見せ告げられた 女の微笑みながらも眦(まなじり)より流れ出た涙の 誇りのそれ、喜びのそれ、さてそれとも。 クトゥは月の子、太陽の子。 すなはち千の長きの年月を、平安に身を置くクシュルファ国と かの地を守護するひとつ神。 そのあわいに在り楔(くさび)となる者。 一等高きに位置する石造りの神殿のなか 使い女(め)達のみと共に過ごす日月の如何なるものか。 夏に至る日、冬に至る日、春を分ける日、秋を分ける日。 年に四度執り行われる祭祀の際 三歳の幼きにして 己の身と同等の重さもあろう黄金に身を飾り あまたの民衆を前に現したその姿の 輝くばかりの愛らしさと神厳の織り重なる様に 「クシュルファ・クトゥ!」の歓声何時までも響き止まず。 次にことりと歯車の 鳴ったであろうのは それより十(とお)の歳月を刻んだ ある秋も深まりをみせた曙の頃。 鋼鉄(まがね)の鎖帷子(かたびら)に身を守り 銀に輝くこれもまた鋼鉄の剣(つるぎ)掲げ幾多の兵士襲い来て ただ一度陽の落ちる間もなきままに 王も妃もその頭(こうべ)首桶のなか。 阿鼻叫喚の喧噪ようやく静まりかけた頃 がちゃりがちゃりと石段昇る音の近く近くになり こじ開けられた扉の先頭に立つ男の姿。 その肌 豊饒もたらす天水(あまみず)呼ぶ声奏で 聖なる獣の第三の位置にある蛙の腹の如くに白く その髪 千年の繁栄支え余りある 黄金それそのもののいろに目映く その瞳 そのいろに溢れ輝くと語り継がれる常世の国たる象徴の 宝玉の王たる宝なる 緑玉石を嵌め込んだかのよう。 “あぁ。” クシュルファ・クトゥの口元より 聞き取れぬ程に微かな音(おん)の思わず漏れる。 これではどうにも仕様がない。 万を数える我がクシュルファの屈強たる剣士達も 之等のいろ併せ持つ者相手にどうして剣の振るえよう。 「神殿はここか。」 男の声が石壁の四方に反響する。 千年の時通じあり得なかった、あってはならなかった事。 黄金の座より立ち上がり クシュルファ・クトゥは意を決する。 様々の宝玉に彩られる黄金の短剣握り締める右手。 その細き手首を軽々と捻りあげ短剣を 地に落とさせた男の動きは さながら稲妻の如くの疾さ 重き帷子に身をくるむ者とは到底思えぬ。 さてこの瞬間(とき) クシュルファ・クトゥの歯車はまたひとつ ことりと音を立てたであろうか。 重きに必ず沈(ちん)をみると 誇らしげな高き笑い声のなか語られた 陥落ちたクシュルファ国所有のありとあらゆる黄金財宝と共に クシュルファ・クトゥは威風堂々に美事な帆船に積み込まれる。 季節のひとつ移りゆく長き時 十六方をただ海(わだつみ)ばかりの中に過ごし ように辿り着いたその場所は肌に薄ら寒く 真冬なれば仕様事もと思えばこれが夏の盛りと聞けば 四季のうつろう順序まで 海に囚われの身の間(ま)に さかしまと成るのかとの眩惑のなか やはり太陽は厚き雲より後ろに隠れおおせたままその姿を見せず。 そうして何より真白き肌の人々の あちらこちらとせわしなく 行き交う様の 何とも息の詰まるよう。 これはまこと同じ世界の有様か。 いつしか船ごと隔世(かくりよ)に 紛れ込んでしまったのではあるまいか。 同じ石造りとてこうも違いのあるものか。 四方に塔の聳え旗翻る荘厳たる屋敷。 その二階の一角に何人もの従女と共に クシュルファ・クトゥは広々とした住居を与えられる。 「恵まれたるクトゥ様は 幸運の女神の御寵愛を一身に賜れておられるかのよう。 次の王となられるヴェリアスティ伯はかのごとく寛恕の御方。 このような手厚い待遇を、例え神に仕える御身であったとしても 我が手に滅した国の女性に与えるなどとは。」 クシュルファ・クトゥの 何物にも興味を示さぬかの瞳が ほんの一瞬きらりと光る。 「あの男は次王(つぎおう)なのか。」 ことり……その時 歯車の回る音が クシュルファ・クトゥのなかにも響きわたったか。 従女達のくすくすと罪のない笑い。 「あれあのように御懇意にされておいでなのに御存知ない。」 慣れぬドレスの着付けに忙しく手を動かしながら ひとりの女が話し出す。 「現王は御世継ぎに恵まれず。 そこで次なる御触れを出されたのが そう、もう二年も前の春の頃。 “此の世の何処かに在るという黄金郷。 そを見い出し財宝を持ち帰った者を 現状の身分問わず王位継承の第一位とす。” と。」 またひとりの女が続けて言う。 「莫大な財産の持ち主ならずば まず船造りの着工より既に及ばぬ事。 そうして富、冒険心、人徳、時間、屈強な心身に恵まれた 野心に燃える貴族の若者達の 向こう見ずな数名の その無謀な冒険に出発し 生きて戻ったのは現在その内唯二名。」 またひとりの女。 「黄金財宝の山と 生き証人となる貴女様を御連れ戻られたヴェリアスティ伯に 現王はいたく感銘され 次王の座を確約する王位継承の儀 王族の血を継ぐラスタシア公爵令嬢との御婚約の儀を兼ねての 三日をあげずの盛大なる祝宴の内に済まされたのが つい先日のこと。」 何と喧(かまびす)しい……クトゥは思わずにいられない。 クシュルファに於いては使い女の 誰一人このように無駄口を叩く者など居なかった。 唯教義を教示する者の声のみの響きわたり 必要不可欠と判断された質問にのみ答えを与えられた。 神殿のなかには夜昼を問わず 静謐ばかりが底を深々(しんしん)と漂っていた。 「ほら姫君の出来上がり。」 「まぁ白いドレスの小麦の肌に映えて何と美しいこと。」 「本当に。 蛮族の娘様と御聞きした時には 正直怖気(おぞけ)もふるったものでしたけれども こんなにも御綺麗で礼儀弁(わきま)えのある御嬢様であられるとは。」 「聞けば長の航海の間に我が国の言葉習得されたとか。 才色兼備の賢姫であられればこそ 伯も斯様(かよう)愛おしく御想いになられるのでしょう。」 此処に来て初めて見た 鏡の映し身。 私とはこのような生き物であったのか これはこの者達の云う様 “美しい” 様(さま)なのか。 「それにしても……。」 従女のひとりの視線が動く。 「それはいまだ 肌身離さずにおられぬ御物でありましょうか?」 細き首より掛けたる 輝く黄金の鞘に収まる美事なる短剣 神殿にてあの男が払い落とした。 「御就寝の折りはもとより 湯浴みの際にも決して御放しにはならないのですから。」 その鞘より抜き取れば 室内の沈んだ光のなかにも尚輝きを散らす金の短剣 その先端を唯一度指でなぞり またすぐに鞘に収めたクトゥは 視線を窓の外へと移す。 まるで痛々しいばかりに 唯一片の狂いもなく手を施され刈り込まれ さながら押し型に嵌め込まれたかの 緑濃い幾何学の紋様。 それがあちらこちらの樹木、樹木に取り囲まれて 彼方地平まで ただ緑の、敷織物のような緑の続く。 「唯これのみが私の私である証。」 誰の耳にも届かぬほどの ちいさな呟きを発しながら クシュルファ・クトゥはまたしても思いに沈む。 十月十日のその間 命慈しみ育みくれた女の宮より此の世に姿現すと この神妙(たえ)なる力与えられた短剣にて 女との繋がりの緒を断ち切ればその瞬間(とき)の 正にクシュルファ・クトゥの誕生となる。 その刃先にはいまだ 我が母なる者の血の沁みついている気の クトゥにはしてならぬ。 人なる母の、ひとつ名を持つ人の、我身と血を繋ぐ者の。 「ははぁ。」 嘶(いなな)き両の前足を高く跳ね上げる馬を前に その身思わず強張らせるクトゥを見遣り 乗馬服に身を包んだヴェリアスティ伯は 微笑みに翠玉の瞳細く 手綱を取る。 「傍に見れば結構な大きさに驚くのも無理からぬ。 だがもとより温厚に優しい気性の生き物。 その上にも充分な調教の施されている故に 何も恐れる事はない。」 その言の葉の終わらぬ内に 伯は早くも騎上の人。 其処よりクトゥに手を差し延べれば その手を取ると同時に細き腰 伯付きの馬丁にひょいと持ち上げられ あっという間に伯の前に横座り。 「慣れぬ衣装では尚落ち着かぬことだろう。 遠慮をせずにその腕 我身に回せば良い。」 初めて乗る馬の背の、なんと視線の高くなり 風の爽やかに緑の、空の、あらゆる香りを運び来る。 揺れの最初はとても恐ろしかったけれども 伯の気遣う手綱のさばきに極めて忠実な並足の その調子の一律なるは 船中に初めて目にした時計の針の刻むが如く。 そうしてその度揺れる栗毛の鬣(たてがみ)の 鈍い太陽の光を浴びて美しく あらゆるものが新鮮に なにもかもが、そう、心地よい。 馬の長い鼻面をつけ水をはむ細流(せせらぎ)に ゆらゆら揺れる二本に並ぶ 淡く長く尾をひく影。 「あの地平の先までもが次王の地か。」 此処はもう あの窓より眺めた地平よりも先の地か。 それさえも判然とせぬ茫漠の緑、また緑 聞こえるのは唯せせらぎと鳥達の囀り。 「その呼び名が余程気に召したと見える。」 くすりと微笑む緑玉石の視線もまた地平の彼方。 「元は亡き父上の、それより先には祖父の所有。 羊皮紙に署名血判を成したところで 感慨も、喜悦の感のひとつも湧きはせぬ。」 「それで次王の立場欲したのか。」 は……と それは自嘲気味な 或は自虐的な 半ば呆れたかの口元歪めた嗤顔。 「そのとおりだ。」 茜に染まりつつある雲を瞳に 伯のこころは彼方へと。 反吐を吐き尽くすまでに吐いた長き航海。 煉獄とは斯くもあらぬとばかりの ありとあらゆる叫び声の昼夜構わず飛び交う 鬱蒼たる原生林。 疲弊の果てぽかりと穿たれた穴のように 突如その姿現した黄金郷。 燦々と照りつける太陽のもと 整然たる金色(こんじき)に輝く建造群。 そのあまりの美しさ 忘我に立ち竦んだのは部下達とて同じこと。 ただ一瞬にして魅入られた。 「クシュルファ・クトゥ。」 伯の瞳はまだ彼方。 「私を憎んでいるだろう。」 そうしてようやく此方を向く。 「憎悪が当然、怨嗟が道理。 言い訳などある筈も無い。 欲する物が在れば言うがよい。 出来る限りを与えよう。」 「次王。」 ゆるやかに戦(そよ)ぐ風になびくは 濡羽の黒髪。 「私は誰も憎まない。」 視線があがる。 「……は。」 この瞳だ。 この黒曜石の瞳。 血塗られし征服欲に高揚し切り 滾(たぎ)る血潮に 脳も体躯も快楽(けらく)にまみれ。 その瞬間(とき) この瞳に対峙した。 たかだか十三歳の少女の、これが瞳(め)か。 一歩。 ヴェリアスティ伯の躙(にじ)り寄れば 手を掲げればクトゥの顔はもうすぐそこ。 その人差し指をそっとクトゥの やわらかきくちびるに押しあてる。 ぴくり、と瞬時反応する小麦色の体躯。 「触れられるのはまだ厭うか。」 クシュルファ・クトゥの歯車の この時も音をたてたであろうか。 翠玉のいろを受け止めていた漆黒の瞳の 長い睫(まつげ)がすぅと覆う。 伯の手がそっと左の顎(あぎと)に移りゆき その金色(こんじき)の髪揺らいだと思えば 今 指をあてがったその温かき真朱(まそほ)のいろに ほんの一瞬くちびる重ね 緑の瞳にじっとその表情(かお)見つめたのちに 次には深く、深くくちづけた。 夜伽のあとの静寂のなか クトゥがその手を 白く湿る伯の左の胸にそっと滑らせば とくん……とくんと脈打つ鼓動。 その掌(てのひら)に直に伝わる。 そうして脳裏に蘇る……体のなかに蘇る。 深き森林に囲まれた美しき祖国クシュルファ。 年に四度の祭祀 唯その為に クシュルファの精悍なる男達は剣を取る。 月白の刻より開始される闘いの 最後に勝鬨の雄叫び高らかな その者のみに 祭祀場へと続く階段の錠は開かれる。 黄金に身を飾るクシュルファ・クトゥの立つ御前に 誇り高き強者(つわもの)の心の臓腑 手早く取り出され 即座クトゥのちいさき掌に。 生温かく腥(なまぐさ)く 生命の余韻蠢く魂の容れ物を 蒼穹高く突き上げれば 今や遅しと待ちかねて 黒き影 地に舞い舞わせ旋回り続ける 天(あま)の使いたる大黒鳥(おおくろとり)の 疾風の速さに舞い降りて 漆黒の濡羽撒き散らし 蹄にそれのみ掴み上げればその瞬時 高き、高き天へと舞い上がり 神の元へと運びゆく。 こうして勇者の魂 神おわす常世の国に。 その強き魂 神の享受賜れば クシュルファの栄華 神の元に約束さる。 太古(いにしえ)よりの仕来たりに 王なる身分にて神殿に入(い)るべからず クトゥの身分にて王宮に入るべからず。 だが若き世継ぎたる次王のみは その性が男ではない故もあり 神殿への出入りを 使い女の他唯一人許された。 このクシュルファ・クトゥに課せられた 幼女には耐えるに過ぎる重責を 果たした後には必ずに 寝室に横たわるクトゥの元を訪れて 人払いひとつ叶わぬなか ねぎらいの言葉をかけ 時にはその柔らかく優しき腕に抱き締めた。 次王の訪問は常に短くほんの一時ではあったが そのひととき ただそれだけが── 「どうした?」 思わず知らずクトゥの眦より一筋に 頭(こうべ)あずけていた伯の 白き右胸に涙の滲めばそののちそれは クトゥそれ自身もがその訳も分からぬままに 滂沱へと嗚咽へと止め処を知らぬ。 「無理をせずとも良いと言うのに。」 半身を起こしヴェリアスティ伯は 小麦色に美しい肌 嗚咽に揺らすクトゥを腕(かいな)に抱き 濡らす涙の止まらぬ頬に額にくちびるに 幾度となく優しくくちづける。 それからどれだけの時が流れたか。 「次王。」 涙に曇る声はまだ幼き童女のよう。 「願いがある。」 首より下がる宝玉のちりばめられた金色の短剣 その鞘を握り締め言の葉を 絞り出すかにちいさく しかし決然とした口調に 黒曜石の瞳一心に 真白き絹の寝具を見据え告げるその様は 夜伽を自らに申し出たその時と 一寸の違いもないと伯は思う。 「約束したな。 出来る限りを叶えよう。」 ことり。 歯車の奏でる音を クシュルファ・クトゥは その心の臓腑の鼓動のなかに はっきりと聞き取ったに違いない。 「私に名前を与えて欲しい。」 さてその瞬間 クシュルファ・クトゥの歯車は 形骸留めぬまでに粉砕されはするのだけれど 次には其れ等の欠片集結した ひとりの少女の歯車の 瞬きの間に形成され ゆっくりとその回転を始めゆく。 ことり……。 |
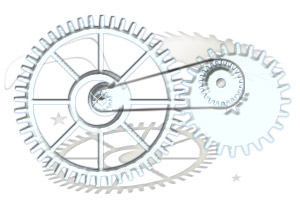
-end-
|
-back ground music- Renaissance "Scheherazade and other stories" |
 作品『クトゥの歯車─次王』あとがきはこちら
作品『クトゥの歯車─次王』あとがきはこちら

Copyright(c)2006 moon in the dusk All Rights Reserved.
著作権に関する考え方については こちらをご覧下さい



